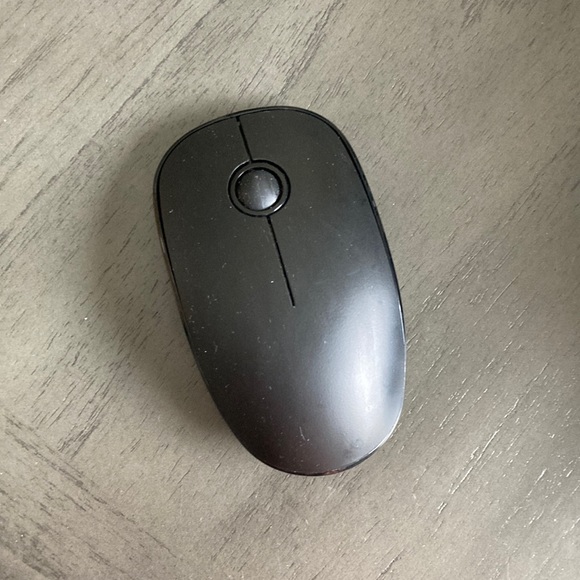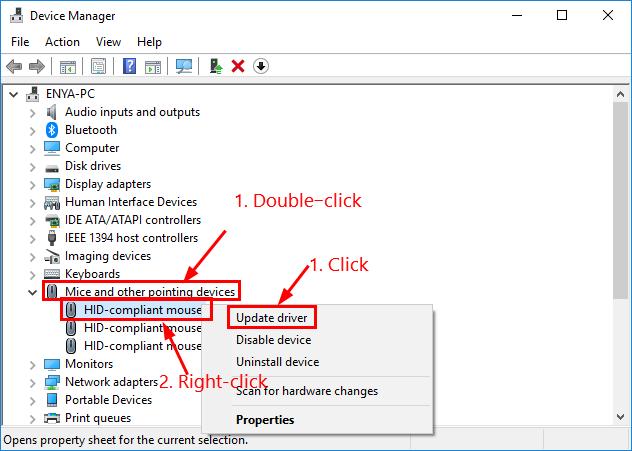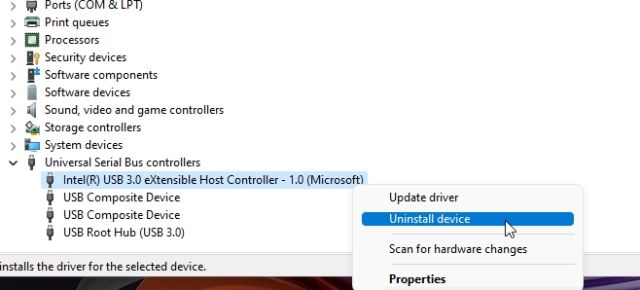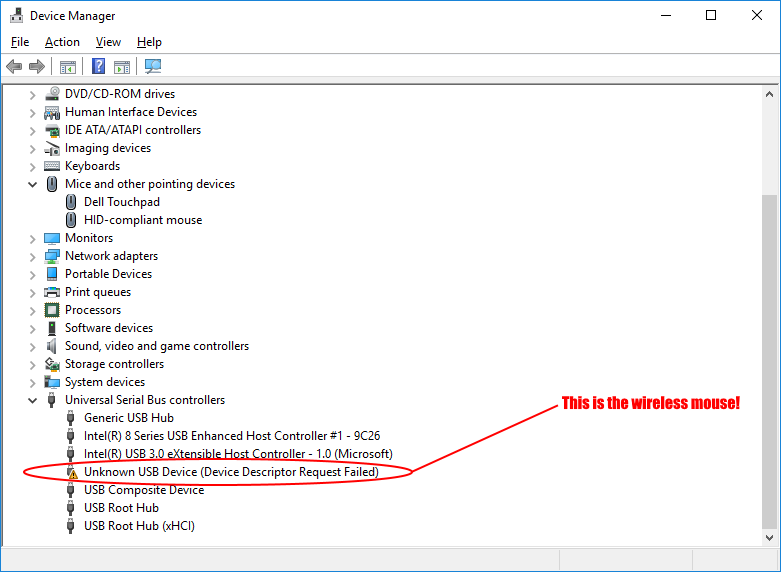Source 2.4G Wireless Optical Mouse Driver, Ergonomic USB Minnie Computer Wireless Mouse on m.alibaba.com

Amazon.com: Wireless Keyboard and Mouse Combo, 2.4G Full-Sized Ergonomic Keyboard Mouse Wireless,3 DPI Adjustable Cordless USB Keyboard and Mouse,Full Numpad,Quiet Click for Computer/Laptop/Windows/Mac : Electronics